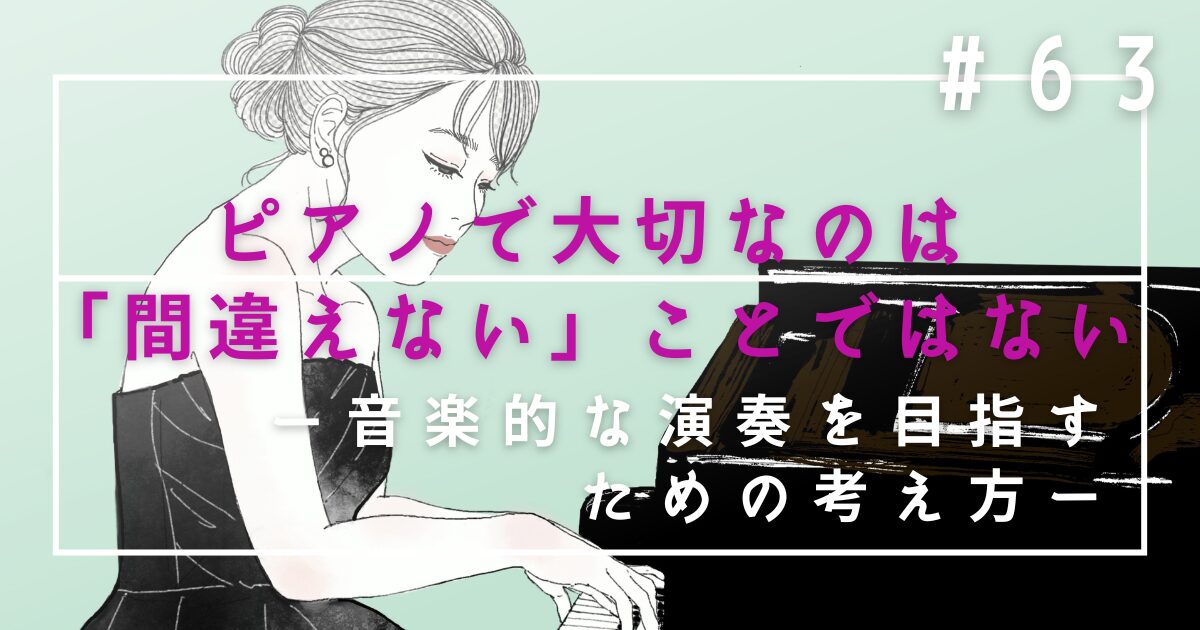ピアノを弾くとき、「間違えないように」と強く意識していませんか?
もちろん正しい音を弾くことは大切ですが、そればかりに気を取られてしまうと、音楽がただの「音の並び」になってしまいます。
実は、ミスのない演奏を目指すより、音楽的な演奏を目指した方が、結果的にミスが減るのです。
なぜなら、作曲家が書いた一音一音には意味があり、その意味を理解して大切に弾くことで、自然と集中力と意識が高まり、演奏が安定してくるからです。
4歳からピアノを始めて音高・音大・音大の院に進み、大人子ども含め累積約50名以上にピアノを教え、現役で演奏活動を続ける筆者が、
「ミスを恐れる」練習から「音の意味を考える」演奏へと意識を変えるヒントをお伝えします。
“間違えないこと”を目標にすると、音楽が止まる
ピアノを学ぶ人の多くがミスを減らそうとするあまり、指の正確さばかりを追い求めてしまいます。
ですが、どんなに練習を重ねても、人間の演奏に「完全なミスゼロ」はありません。
むしろ、「間違えないように」と考えるほど、体が硬くなり、呼吸が浅くなり、結果として思わぬところで指が止まってしまうことが多いのです。
この状態では、音楽が流れなくなり、聴いている人にも「緊張感」しか伝わりません。
そうではなく、大切なのは「この音にはどんな意味があるのか」「なぜここで和音が変わるのか」「作曲家はどんな気持ちで書いたのか」を感じ取ること。
それを意識して弾くことで、自然に音楽が息づき、ミスへの恐怖は薄れていきます。
音の意味を感じるとはどういうことか
たとえば、ベートーヴェンの《ソナタ第14番「月光」》の第1楽章。
ただ正確に弾くだけでは、静かな三連符の流れが単調に聞こえてしまいます。

「月光」という名前はベートヴェンがつけたものではありません。
ベートーヴェンが当時想いを寄せていた、ジュリエッタ・グイッチャルディにこの曲はささげられています。
最初の三連符は、歌が入ってくる前の、沈鬱ながらもどこか美しい雰囲気づくりに欠かせません。
「月の光」をイメージするより、「大切な人を想う気持ち」を込めて演奏するべきです。
ミスを意識しすぎると、作曲家の声が聞こえなくなる
作曲家は、ひとつひとつの音に意図があって楽譜を書いています。
もしあなたが演奏中に「間違えないように」とばかり考えていると、その意図を感じ取る余裕がなくなってしまいます。
言い換えれば、ミスを恐れるほど、作曲家の声を聞くことができなくなるのです。
「この音はなぜここにあるのか」と考えながら弾くことで、音に“説得力”が生まれます。
そうして音を大切に扱うようになると、指も自然に慎重かつ滑らかに動くようになります。
つまり、音楽的に弾こうとする姿勢こそが、ミスを減らす最良の方法なのです。
私も自分自身に言い聞かせています
このように言う私も、暗譜やミスへの恐怖はあります。
「練習でも苦手だったあそこ、弾けるだろうか…。」
「音を忘れてしまったらどうしよう。」
練習の時も、本番の時も、思ってしまうことがあります。
ですが、私は一度立ち止まってこう考えます。
「私が演奏する意味とはなにか。」
「ミスにおびえて、なんとか弾き切ることが私がピアノを弾く意味なのか。」
そうではないはずです。
作曲家が音に込めた想いを聴いている人に伝えるために、私たちは人前でピアノを弾きます。
不安にとらわれそうになったとき、私はいつもこのことを思い返しています。
「なぜ人前でピアノを弾くのか」
あなたも、練習中や本番前に自分に問いかけてみてください。
そうすれば、目の前の音に集中できるはずです。
まとめ
ピアノで大切なのは、「間違えない演奏」ではなく、「伝わる演奏」です。
作曲家の意図を感じ、一音一音に意味を見つけて弾くことができれば、自然と音に生命が宿ります。
ミスを恐れる気持ちは、誰にでもあります。
けれど、音の意味を大切にしながら弾けば、ミスは減り、音楽は豊かになる。
音を間違えることよりも、「作曲家が伝えたかったことを、どれだけ聴き手に伝えられたか」——それこそが、本当の意味での“上達”なのです。
★お知らせ★
私のピアノソロリサイタルが、11月1日(土)13時~ より埼玉県の与野本町にある「彩の国さいたま芸術劇場小ホール」にて開催されます!
バッハ、ショパン、ラフマニノフ、ベートーヴェンと幅広い作曲家の作品を演奏します。
チケット絶賛お申込み受付中です。
お申し込みの際は、office@sakuramusic.jp、もしくはこちらのブログの問い合わせフォーム、またはコメントよりお願いいたします。
ご来場、心よりお待ちしております。