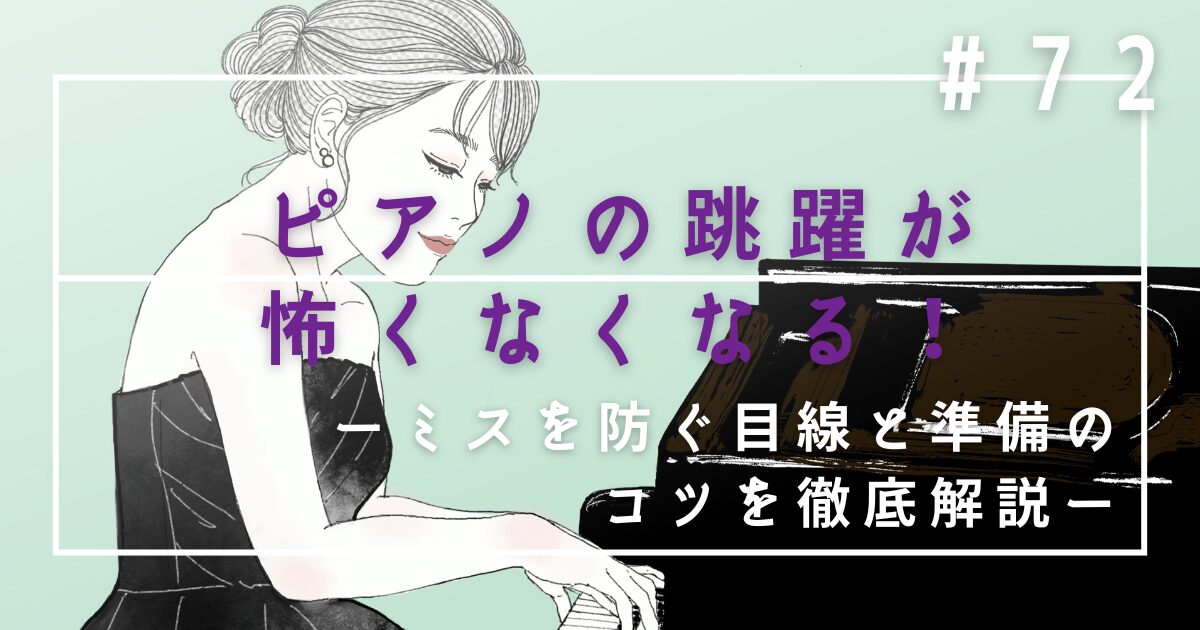ピアノを弾いていて、「跳躍のときに外してしまう」「次の音の位置がつかめない」という経験はありませんか?
特に中級者以上の曲では、片手または両手で大きく鍵盤を移動する場面が多くなり、跳躍に苦手意識を持つ人も少なくありません。
しかし、跳躍の安定には“指の速さ”よりも“目線”と“準備”が重要です。
4歳からピアノを始めて音高・音大・音大の院に進み、大人子ども含め累積約50名以上にピアノを教え、現役で演奏活動を続ける筆者が、
跳躍を安定させるための実践的なコツを具体的にご紹介します。
跳躍を安定させるために大切なのは「目」と「準備」
手ではなく“目”が先に動く
跳躍の苦手な人の多くは、手を動かしてから次の位置を探す癖があります。
実は、これでは間に合いません。
安定して跳躍できる人は、音を弾く前にすでに目線が次の位置へ移動しているのです。
目で鍵盤の位置関係をつかみ、空間の距離感を先に「視覚で覚える」ことで、手の動きが迷わなくなります。
🔹練習のコツ
- 跳躍直前に次の着地点を見る練習をする
- 手ではなく、視線の移動を先に行う
- 慣れるまではゆっくりテンポで「見る→弾く」を繰り返す
この「先を見る」だけで、跳躍の成功率が格段に上がります。
音を弾く前に“準備”しておく
跳躍では、次の位置を見たあとに手をすぐ動かすのではなく、腕全体のバランスを移動させておく準備が必要です。
跳躍を支えるのは“指”ではなく、“腕の重心”です。
🔹ポイント
- 手の位置を移動させるのではなく、腕全体を「スライド」させるイメージ
- 跳躍後の最初の音は“腕の重み”で落とす
- 手首を固めず、軽く支えながら移動する
こうした準備ができると、鍵盤に“飛び込む”のではなく“着地する”ような安定感が生まれます。
例:モーツァルト《トルコ行進曲》の場合
たとえばモーツァルト《トルコ行進曲》では、右手がオクターブや和音で素早く跳躍する箇所が何度も出てきます。

このときに鍵盤を“追いかける”ように見てしまうと、手が遅れて外れやすくなります。
代わりに、次のオクターブの位置を先に目で確認し、「目が先、手があと」を意識してみましょう。
テンポを落としてでも、この順序を体に覚えさせることが安定の第一歩です。
さらなる跳躍のコツ
跳躍するときは上に手をあげるのではなく、ちょっと鍵盤から指を離して真横にスライドして弾くのがコツです。
最短距離で移動することで、余計な力や時間をかけずに済みます。
このようにすることで、速いテンポでの跳躍移動も可能になります。
前提として、「先に目線を配る」「音と音の距離を感覚的に覚える」必要はあります。
跳躍の距離感をつかむ練習法
① 距離を測る練習
鍵盤を見ながら「ド」→「ド」のオクターブを、リズムを変えて何度も繰り返します。
② ノールック練習
見ずに弾いて外れたら、距離感のズレを確認。感覚を身体で覚える練習です。
③ 左右別練習
両手での跳躍より、まずは片手ずつで感覚を身につけてから合わせると安定します。
筆者の経験談
生徒さんを教えていて、跳躍に苦戦する姿をよく見かけます。
だいたいの場合は、移動してから次の音を準備しているせいだと感じています。
音楽はどんどん流れていくものなので、そこにきてから用意するのでは間に合いません。
常に「早めの準備」が大切になります。
生徒さんに跳躍の前に「目線を配って」と一言声をかけただけで、移動がスムーズになることは多いです。
視覚に頼りすぎるのは危険ですが、とても効果的な方法だと考えます。
慣れてきたらノールックでも移動できるようにはなります。
まとめ:跳躍は“飛ぶ”のではなく“移る”感覚で
跳躍がうまくいかないとき、私たちはつい“指を速く動かすこと”に意識が向きがちです。
しかし、本当に大切なのは「見る」ことと「準備する」こと。
跳躍の成功は、視線の先行と腕全体の重心移動で決まります。
この2つを意識するだけで、跳躍への恐怖感は驚くほど減り、鍵盤を“渡っていく”ように弾けるようになります。
毎日の練習の中で、少しずつ「目が先、手があと」を意識してみてください。
それだけで、跳躍はあなたの味方になります。
★お知らせ★
私のピアノソロリサイタルが、11月1日(土)13時~ より埼玉県の与野本町にある「彩の国さいたま芸術劇場小ホール」にて開催されます!
バッハ、ショパン、ラフマニノフ、ベートーヴェンと幅広い作曲家の作品を演奏します。
どれも思い入れのある作品ばかりです。
チケット絶賛お申込み受付中。
お申し込みの際は、office@sakuramusic.jp、もしくはこちらのブログの問い合わせフォーム、またはコメントよりお願いいたします。
ご来場、心よりお待ちしております。