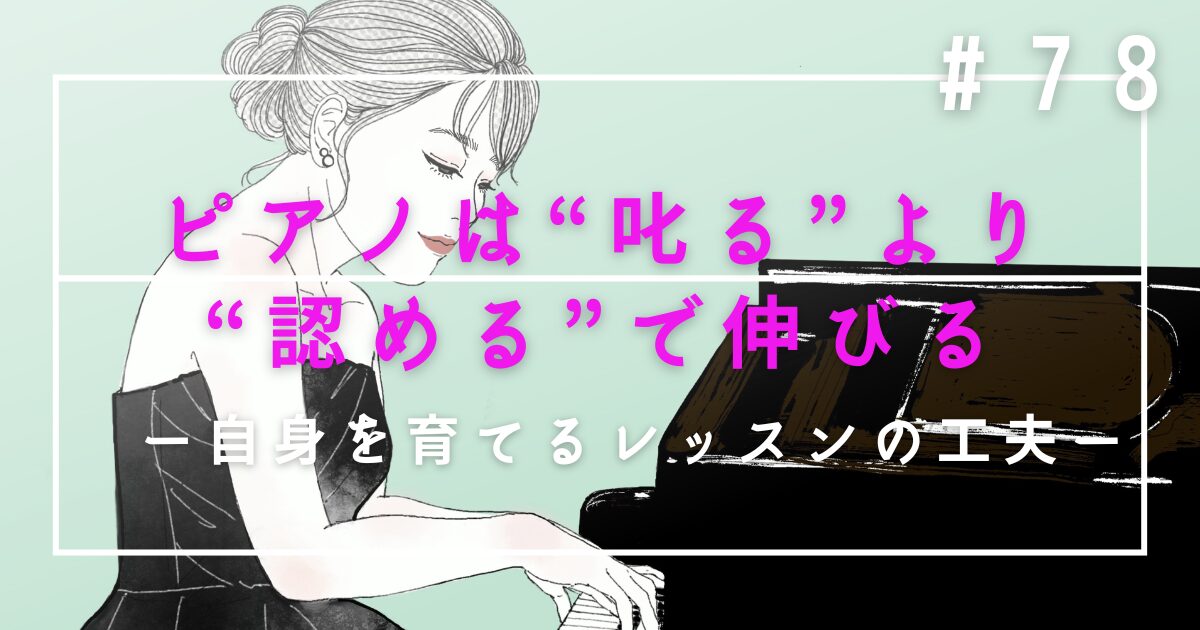ピアノの上達には、技術だけではなく「音楽が好き」という気持ちも欠かせません。
どんなに指が速く動いても、心なくして音楽は育ちません。
レッスンの中でできないことがあっても、焦らず、自信を失わずに続けることが何より大切です。
私は、どんな生徒にも「弾けるようになる力」があると信じています。
そのために心がけているのが、「褒めて伸ばす」「共感して一緒に取り組む」ということ。
生徒の心が動く瞬間を大切にしながら、日々ピアノを教えています。
4歳からピアノを始めて音高・音大・音大の院に進み、大人子ども含め累積約50名以上にピアノを教え、現役で演奏活動を続ける筆者が、
「生徒の自信を育てるレッスンの工夫」について解説します。
なぜ“褒めて伸ばす”ことが大切なのか
ピアノの練習は、“できない瞬間”の連続です。
そこから練習を積み重ねてこそ上達につながりますが、そこで「なんで弾けないの」と叱ってしまうと「次に挑戦しよう」という気持ちが消えてしまいます。
反対に、
「ここまでできたね」
「あともう少しで弾けそう!」
そんな言葉をかけると、もう一度やってみようという意欲が生まれます。
褒めることは甘やかすことではありません。
できた部分を見つけて言葉にすることで、生徒が自分の力を実感できるようになります。
その「できた!」という小さな自信こそが、次の成長のエンジンになるのです。
“その気にさせる”声かけの工夫
レッスンで意識しているのは、具体的に褒めることです。
「上手だね」だけではなく、
「今の音、とてもきれいに響いたね」
「さっきよりも指が軽く動いたね」
と具体的に伝えるほうが、生徒は自分の成長を実感できます。
また、つまずいたときには、
「失敗しても大丈夫。先生も最初はそうだったよ」
と共感のひと言を添えます。
そして、できたときは少しオーバーに喜びます。
一緒に笑って、「やったね!」と声をかけると、生徒は「もう一回やってみよう」と意欲的になります。
「できない」ときの向き合い方
レッスンで「できない」という言葉が出たとき、私はまず「どうしてできないの?」とは聞きません。
代わりに、
「どの音が難しいかな?」
「どの指が動きにくい?」
と一緒に考えます。
問題を一緒に探すことで、「叱られる」とおびえさせるのではなく、前向きに練習へと導きます。
小さな進歩を見逃さず、「今の一音、すごくよくなったよ」と伝えることで、
“できない”が“これから伸びるサイン”に変わっていきます。
自信を持つ瞬間を大切に
そうして「できた!」という達成感を重ねていくうちに自信が生まれ、少しずつピアノの上達へと近づいていきます。
生徒さんには、「やらされている」のではなく「自らやっている」という認識をもって練習してもらいたいと思っています。
そのためにも弾けないときは励まし、弾けたときには一緒に喜ぶ。
教えるときには、特にこのことを大切にしています。
【筆者の経験談】
ピアノの先生の役割は、ただ教えればいいというものではないと思います。
「私もやってみたい」と思わせ、自ら興味をもって練習できるように導くという役割もあるはずです。
なぜ私がそのようなレッスンと心がけるようになったかというと、私自身がそのように育ててもらったからです。
私に最初にピアノを教えてくれた先生は、とにかく褒めてくださる先生でした。
「大丈夫、ちなみちゃんならできる。」とたくさん励ましていただき、
それが私の力となって、練習する原動力になっていました。
「褒められるから練習するというのは違う」という人がいるかもしれませんが、
「褒められるのが練習のモチベーションにつながる」というのでも私は良いと思います。
練習へのひとつのきっかけになれば、それでいいのです。
まとめ|先生の一言が未来を変える
ピアノの技術は、時間をかければ誰でも身につけることができます。
でも、「自分はできる」と信じる気持ちは、まわりの言葉によって育まれます。
生徒の中にある小さな芽を見つけて、水をあげるように育てていく。
その芽がいつか、大きな音楽の花を咲かせる日を信じて──。
これからも、「叱る」より「認める」レッスンで、生徒の自信と音楽を育てていきたいと思います。
★お知らせ★
私のピアノソロリサイタルが、11月1日(土)13時~ より埼玉県の与野本町にある「彩の国さいたま芸術劇場小ホール」にて開催されます!
バッハ、ショパン、ラフマニノフ、ベートーヴェンと幅広い作曲家の作品を演奏します。
どれも思い入れのある作品ばかりです。
チケット絶賛お申込み受付中。
お申し込みの際は、office@sakuramusic.jp、もしくはこちらのブログの問い合わせフォーム、またはコメントよりお願いいたします。