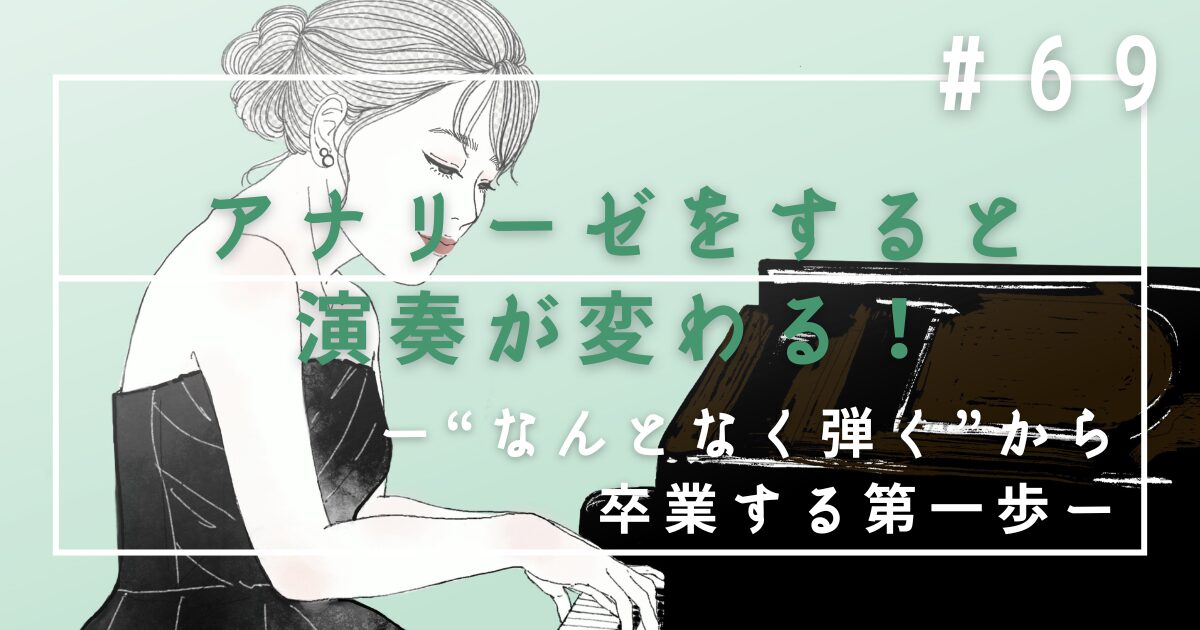ピアノを弾いていて、「最後まで弾けるようにはなったけれど、何か物足りない」と感じたことはありませんか?
それは、“音を並べて弾いているだけ”になってしまっている可能性があります。
音楽には「流れ」「方向」「感情」があります。
それを理解しないまま弾くと、どんなにミスがなくても“平板な演奏”に聞こえてしまうのです。
その“なんとなく弾く”状態から抜け出すための第一歩が、アナリーゼ(分析)です。
アナリーゼは、作曲家がどんな意図で音を並べたのかを知るための、いわば“音楽の読解力トレーニング”。
4歳からピアノを始めて音高・音大・音大の院に進み、大人子ども含め累積約50名以上にピアノを教え、現役で演奏活動を続ける筆者が、
初心者の人にもわかる「アナリーゼの活用法」について、解説します。
アナリーゼとは?音の流れを読み解く作業
アナリーゼ(Analyse)とは、曲の構造や和声、モチーフなどを分析して、音楽の意味を理解することを指します。
理論だけでなく、「この曲はどんな性格?」「どこが山場?」「どんな気持ちで書かれた?」と考えることが大切です。
例えば、
- 曲の始まりがどんな調で始まるのか
- 途中で転調して気分が変わっているのか
- どんなリズムや動機(モチーフ)が繰り返されているのか
を観察するだけで、作曲家の意図が少しずつ見えてきます。
具体例:モチーフがいろいろなところに現れる
たとえば、分かりやすい例でいうとブラームスの《6つの小品 Op.118-2》。
この曲はA・B・Aという曲の構成ですが、冒頭の右手のメロディーがAの終わり部分の内声に現れます。
〈Op.118-2 冒頭〉

〈Aの終わり部分〉

明らかにブラームスが意図したこのモチーフの転用を弾き手が意識しなければ、演奏する意味がありません。
隠れたモチーフを探すのは、まるで“隠れミッキーを探すような”わくわくさがあります。
アナリーゼを通して、こういった隠れたモチーフに気づけるようになると、音に意味が宿ります。
調や形式を知ると音楽の地図が見えてくる
アナリーゼをするとき、最初に注目したいのは「調(キー)と形式(構造)」です。
- どの調で始まり、どの調に移るのか
- どこが主題、どこが展開、どこが再現なのか(ソナタ形式の場合)
これをつかむだけで、曲の全体像が見えてきます。
たとえば、ハ長調の曲は明るく素直な印象、イ短調なら少し陰りを感じる響き。
そしてこの二つの調の関係性は、同じ調号を持つ「平行調」。
こういった調の性格や関係性を意識するだけでも、演奏の仕方が変わってきます。
形式を理解すると、「今は曲のどの場面を弾いているのか」がわかるため、
どこに山場を持ってくるか計算し、行き当たりばったりの演奏ではなくなります。
アナリーゼで演奏が変わる理由
アナリーゼを行うと、音を「ただ弾く」から「意味を持って弾く」に変わります。
作曲家が込めた意図を理解できると、自然と音の強弱や間の取り方が変化します。
つまり、理論ではなく感性が磨かれるのです。
ミスを減らすための練習ではなく、音楽を理解して表現するための練習へとシフトしていきます。
体験談:アナリーゼで見えた作曲家の意図
これまでピアノの先生たちによく言われてきました。
「弾くばかりではなく、楽譜を見ろ。」と。
そうはいっても指を動かさないのは不安だし、ついつい習慣でピアノの前に座って弾いてしまいます。
私が高校生のとき、強制的にピアノが弾けない期間が一週間ありました。
なぜ強制的にピアノを弾けなかったかといいますと、とある病気で入院をしていたからです。
治療(手術)が終わった後、入院中とてつもなく暇で、
当時弾いていた、ベートーヴェンのピアノ・ソナタ第21番「ワルトシュタイン」の楽譜を何の気もなしに眺めていました。
その曲の展開部に、調が変わりながら何度も同じリズムを刻む部分があって、
「どうしてこんなにも同じことを繰り返すんだ、ベートーヴェンは。しつこいな~。」
と考えていました。
そこから眺めてるうちに、私の中にある考えが湧いてきました。
「こんなにしつこいということは、それほど思い入れがあるのではないのか。」
とそこにベートーヴェンの執念に近いものを感じました。
音の意味を考えて、初めて心をこめてそのフレーズが弾けるようになったと思います。
翌週に受けたレッスンでも、先生から
「演奏が変わった。どうしたの?」と言われました。(笑)
同じメロディー、同じリズムを刻んでいたとしても、
何も考えずに弾くのと、意味を考えて弾くのとでは、演奏の説得力が変わります。
意味を考えて弾けばそれが聴いているお客さんにも伝わる。
これが私が言う「説得力のある演奏」です。
今回の私の例は、アナリーゼというほどのものではないかもしれませんが、楽譜と向き合うことで得られたポジティブな経験となりました。
それ以降、楽譜と向き合う時間を大切にしたいと常々考えています。
まとめ:アナリーゼは“心で弾く”ための道しるべ
アナリーゼとは、楽譜の裏に隠れた作曲家の思いを探る作業です。
調や形式、和声を少しずつ読み取ることで、曲の流れや感情の起伏が見えてきます。
弾けるようになるだけで満足せず、「なぜこの音なのか」を考える時間を持つこと。
それが、聴く人の心に届く演奏への第一歩です。
“なんとなく弾く”から、“意味を考えて弾く”へ。
あなたの演奏は、きっとそこから大きく変わります。
★お知らせ★
私のピアノソロリサイタルが、11月1日(土)13時~ より埼玉県の与野本町にある「彩の国さいたま芸術劇場小ホール」にて開催されます!
バッハ、ショパン、ラフマニノフ、ベートーヴェンと幅広い作曲家の作品を演奏します。
どれも思い入れのある作品ばかりです。
チケット絶賛お申込み受付中。
お申し込みの際は、office@sakuramusic.jp、もしくはこちらのブログの問い合わせフォーム、またはコメントよりお願いいたします。
ご来場、心よりお待ちしております。