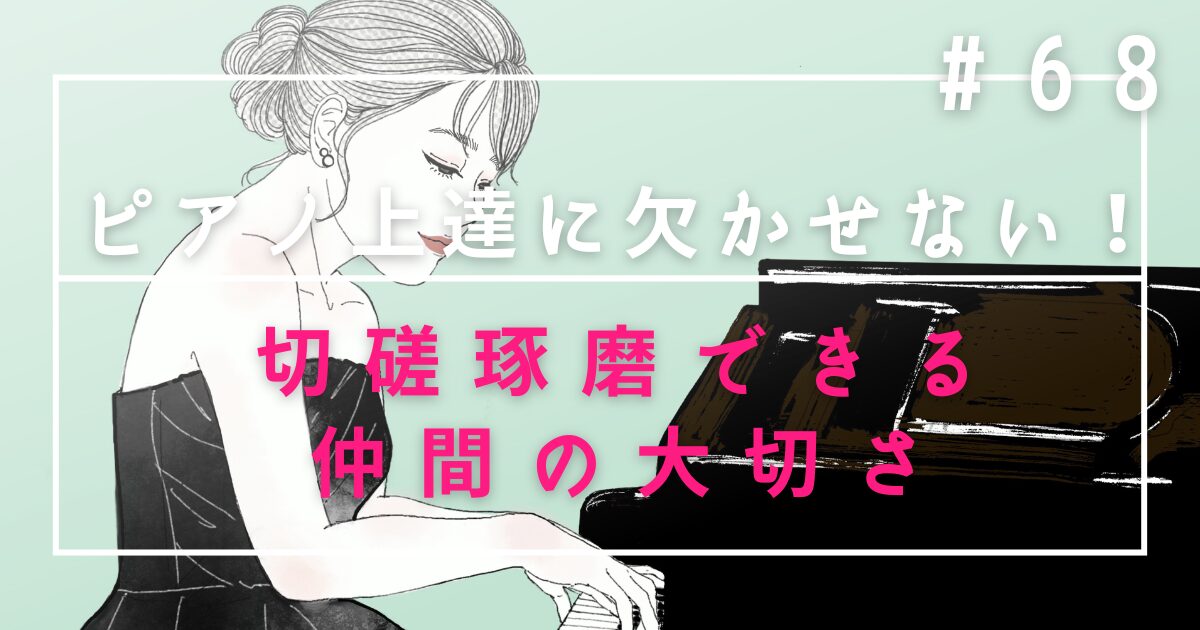ピアノを練習していると、つい自分のペースだけで練習しがちです。
ですが、上達する人の共通点のひとつは「ライバルや切磋琢磨できる仲間を持っていること」。
一緒に学ぶ仲間がいると、モチベーションが上がるだけでなく、演奏の幅も自然に広がります。
4歳からピアノを始めて音高・音大・音大の院に進み、大人子ども含め累積約50名以上にピアノを教え、現役で演奏活動を続ける筆者が、
仲間やライバルの存在がピアノ上達にどのように役立つかをご紹介します。
ライバルの存在で引き出される成長
競争は悪ではない
ライバルがいると、自分の弱点や改善点に目が向きます。
「負けたくない」という気持ちが練習の原動力になることもあります。
「競争することは悪」と言われることもあります。
人と比べるのではなく、自分と向き合うことが大切だと。
たしかにそうではあるのですが、一方で他人の存在が刺激をくれるのもまた事実です。
ただし、注意したいのは「他人に勝つことが目的」にならないこと。
ライバルは比較する相手ではなく、あくまで自分を伸ばすきっかけであり、成長のための刺激です。
具体例:発表会やコンクールでの刺激
たとえば、同じ音楽教室の生徒同士で発表会に出ると、
「同い年くらいの子でこんなふうに演奏できるんだ!」という刺激を得ます。
そうすると、自分も「このフレーズをもっときれいに弾きたい」「表現を工夫しよう」という意識が芽生えます。
これは、他人の演奏を見聞きすることで、自分の演奏の改善点に気づく良いきっかけとなる例です。
切磋琢磨できる仲間のメリット
励まし合い、情報を共有できる
仲間がいると、練習中の悩みや発見を共有できます。
「ここがうまくいかない」と相談すれば、自分では気づかなかったアドバイスをもらえることも。
一緒に学ぶことで、ピアノへの理解や表現力が自然に広がります。
競争心だけでなく学び合いも生まれる
仲間と比べるだけではなく、教え合うことで知識や技術が深まります。
たとえば、ある人がリズムの取り方に工夫をしていれば、それを自分の練習に取り入れることができます。
そして自分の強みだったり知識だったりを相手に教えると、考えがより明瞭になり、自分のなかでさらにそのことへの理解を深めることができます。
「教え、教わる」ことで、お互いにとって好循環が生まれるのです。
ライバルと仲間、どちらも大切に
ライバルは自分を引き上げる存在
ライバルは、自分に必要な“少し背伸びした課題”を示してくれます。
たとえば難しい曲に挑戦する勇気や、表現の幅を広げるきっかけをくれる存在です。
仲間は支え合う存在
仲間は、時には一緒に悩み、時には一緒に喜びを分かち合う存在です。
孤独になりがちな練習時間も、励まし合うことで続けやすくなります。
まだライバルや仲間が見つかっていない人は…
発表会やコンクールに出て同年代の子とぜひお話ししてみましょう。
「緊張するね。」とか「さっきの演奏とてもよかった。」
とか、内容はなんでもいいです。
同じ教室でそういう友達がいたら、それもいいと思います。
音高や音大でなら、ライバル・仲間はさらに見つけやすいでしょう。
筆者の体験談
私にもライバルや仲間がいます。その存在のありがたみを身をもって知っています。
小学生から大学まで、私には同じヤマハ音楽教室で習い、切磋琢磨してきたライバルでもあり戦友でもある友達がいました。
その友達は私よりも優秀で、その子のように私ももっと上手にピアノを弾きたいと、努力を重ねていました。
その子がいなければ、私は間違いなくここまでこられなかったと断言できます。
また、大学の別の優秀な友達たちによく演奏に対するアドバイスをもらっていました。
「こういうふうに弾くといいよ」とか、
ピアノが上手になるために「いろんな人の演奏をきくといいよ。」とか、
私の悩みに真摯に考え、アドバイスをくれました。いまでもとても大切な友達です。
ピアノはほとんどの場合一人で演奏するものですが、決して一人では成長できないものだと心から実感しています。
まとめ
ピアノの上達には、自分だけの努力も大切ですが、
「切磋琢磨できる仲間」と「適度なライバル」の存在が大きな力になります。
仲間やライバルから刺激を受け、学び合い、励まし合うことで、演奏の幅も表現力も自然に広がります。
一人での練習では気づけない成長が、仲間との関わりの中で見えてくるのです。
★お知らせ★
私のピアノソロリサイタルが、11月1日(土)13時~ より埼玉県の与野本町にある「彩の国さいたま芸術劇場小ホール」にて開催されます!
バッハ、ショパン、ラフマニノフ、ベートーヴェンと幅広い作曲家の作品を演奏します。
チケット絶賛お申込み受付中です。
お申し込みの際は、office@sakuramusic.jp、もしくはこちらのブログの問い合わせフォーム、またはコメントよりお願いいたします。
ご来場、心よりお待ちしております。