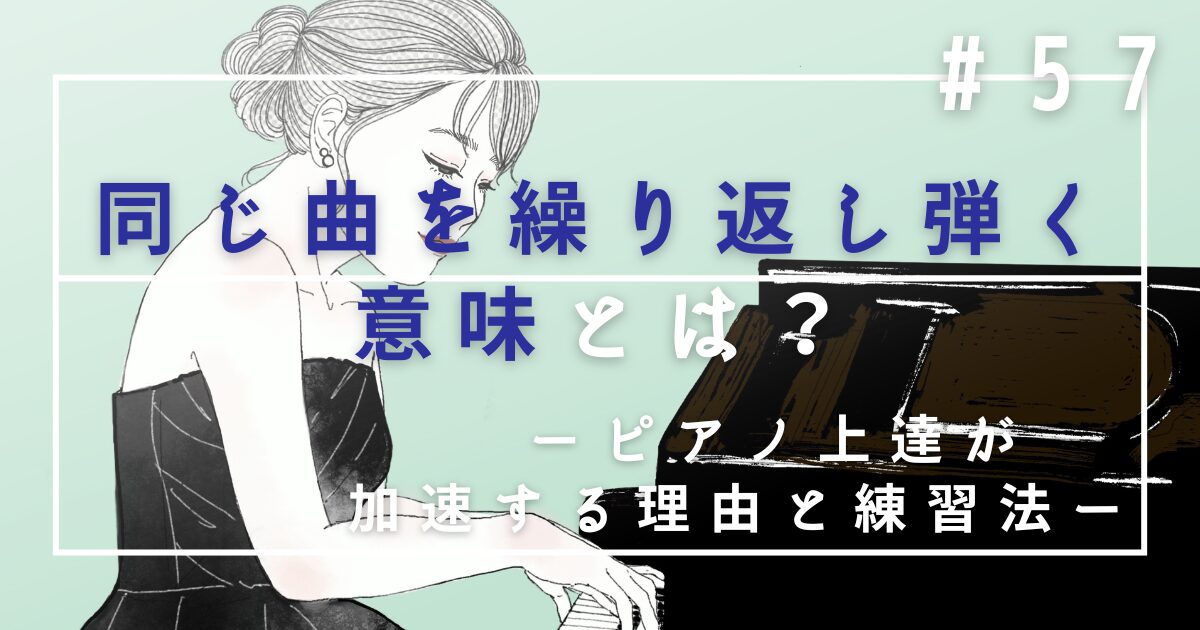発表会やコンクールが終わると、「この曲はもう十分弾いた」「次の曲に進みたい」と思う方は多いでしょう。
ですが、実は同じ曲を繰り返し弾くことこそ、ピアノ上達を大きく支える練習法のひとつです。
一度仕上げた曲を、しばらく時間をおいて再び弾くと、以前とは全く違う感覚で音楽をとらえられるようになります。
音の響き方や表現の幅が自然と広がり、演奏全体の完成度も上がります。
4歳からピアノを始めて音高・音大・音大の院に進み、大人子ども含め累積約50名以上にピアノを教え、現役で演奏活動を続ける筆者が、
ピアノで「同じ曲を何度も弾く意味」について、音の変化・理解の深まり・練習法の工夫など、具体的に解説します。
音の「質」が変わる
初めて練習していたときは、「間違えずに弾く」「テンポを安定させる」ことに集中していたと思います。
ですが、再び弾くと指がすでに動きを覚えているため、音の質や響き方、タッチの細やかさに意識を向けられるようになります。
たとえばショパンの《ノクターン第2番 変ホ長調》を久しぶりに弾くと、以前よりも柔らかな音色でレガートがつながり、音と音の間に呼吸が生まれるのを感じるはずです。
同じ曲を繰り返すことで、自分の音の変化を実感しやすくなるのです。
楽譜の理解が深まる
時間をおいて再び同じ曲を弾くと、以前は見えていなかった構造や和声の流れに気づくことがあります。
「この和音は緊張を生んでいる」「ここで解決して安定している」など、音楽の“意味”が見えるようになるのです。
作曲家がどうしてその音を書いたのか、時間を置くと見えてくるものがあります。
これは単に技術ではなく、音楽的洞察力の成長を示しています。
表現力が成熟する
音楽は、弾き手の心の状態によって変わります。
1年前に弾いたときと、今では感じ方も人生経験も違うはず。
同じ曲でも、テンポの揺らぎや音の重み、間の取り方に自然な変化が出てきます。
ベートーヴェンやブラームスの後期作品では、この「心の成熟」が特に表れやすく、歳を重なるごとに音の深さが増していきます。
それはどうしてかというと、「心の成熟」によって真に音楽に共感して演奏できるようになっているからです。
繰り返し弾くことは、音楽的成長を確かめる鏡のようなものなのです。
再挑戦は短時間練習にも最適
新しい曲を始めるには時間がかかりますが、過去に弾いた曲なら譜読みの負担が少なく、音作りに集中した質の高い練習ができます。
「今日は時間がない」という日でも、以前弾いた曲を数分、数十分さらうだけで、手の感覚や音楽の感度を保つことができます。
比べて気づく「自分の成長」
同じ曲を録音して、以前の演奏と今の演奏を聴き比べてみるのもおすすめです。
音色の違い、テンポの自然さ、フレーズのまとまりなど、思った以上に成長を感じられるはず。
これは自己評価を客観的に行うよいきっかけにもなります。
練習のモチベーションが上がり、次の課題にも前向きに取り組めるようになります。
私が同じ曲を学び直して実際に感じたこと
私がコンサートで演奏するとき、必ずしもすべて新曲を弾いているわけではありません。
もちろん新しい曲も弾きますが、割合として大きいのは以前学んだことのある曲たちです。
コンクールでも上まで勝ち残る人たちは、皆いままでのレパートリーを磨いて臨んでいます。
「同じ曲ばかり弾いていても進歩がない」と思うかもしれませんが、それは違います。
絶対になにかしら「新しい発見」に出会えます。自分の成長にも気づくことができます。
私自身も、期間を置いて曲に取り組み直す度にそう感じています。
一度で終えてしまうのは、
・自分の成長を感じる
・作品への理解が増す
という点においてもったいないです。
ぜひ、積極的に今までの曲に取り組み直してほしいと私は思います。
まとめ
同じ曲を繰り返し弾くことは、決して「停滞」ではありません。
それはむしろ、技術・理解・感性のすべてを磨く最短の上達法です。
一度弾いた曲を時間をおいて再び練習することで、音の深みや音楽の意味をより豊かに感じ取れるようになります。
忙しいときでも、ほんの少しピアノに触れたり、楽譜を眺めて音をイメージしたりすることで、確実に前進していけます。
「もう終わった曲」ではなく、「これから育てていく曲」として、ぜひお気に入りの一曲を何度も弾き返してみてください。
そこに、あなた自身の音楽の成長がきっと見えてきます。