ドミナントではなく「ドッペル」ドミナント?
皆さん「ドッペルドミナント」という音楽用語をご存じだろうか。
前回、和音記号の解説で「ドミナント」という言葉を出しました。
それにさらに「ドッペル」という言葉がついたこれは、いったい何者なのだろうか?
結論:ドミナントの一種であり、ドミナントに行きたいドミナントのこと。(なんだか、なぞなぞのよう・・・)
「ドッペルドミナント」は英語で[Double Dominant]。
つまり「ダブルのドミナント」です。
この記事を読むことでさらに和音に関する理解が深まり、楽曲分析に生かせるようになります!
ドッペルドミナントとは
属七の和音に属七の和音を重ねたもの
属七の和音とは
ドッペルドミナントの解説に入る前に、「属七の和音」について説明します。
属七の和音とは、Ⅴ度の和音【ハ長調ならソシレ】に第7音がついたものです。(青●で示したところが第7音)
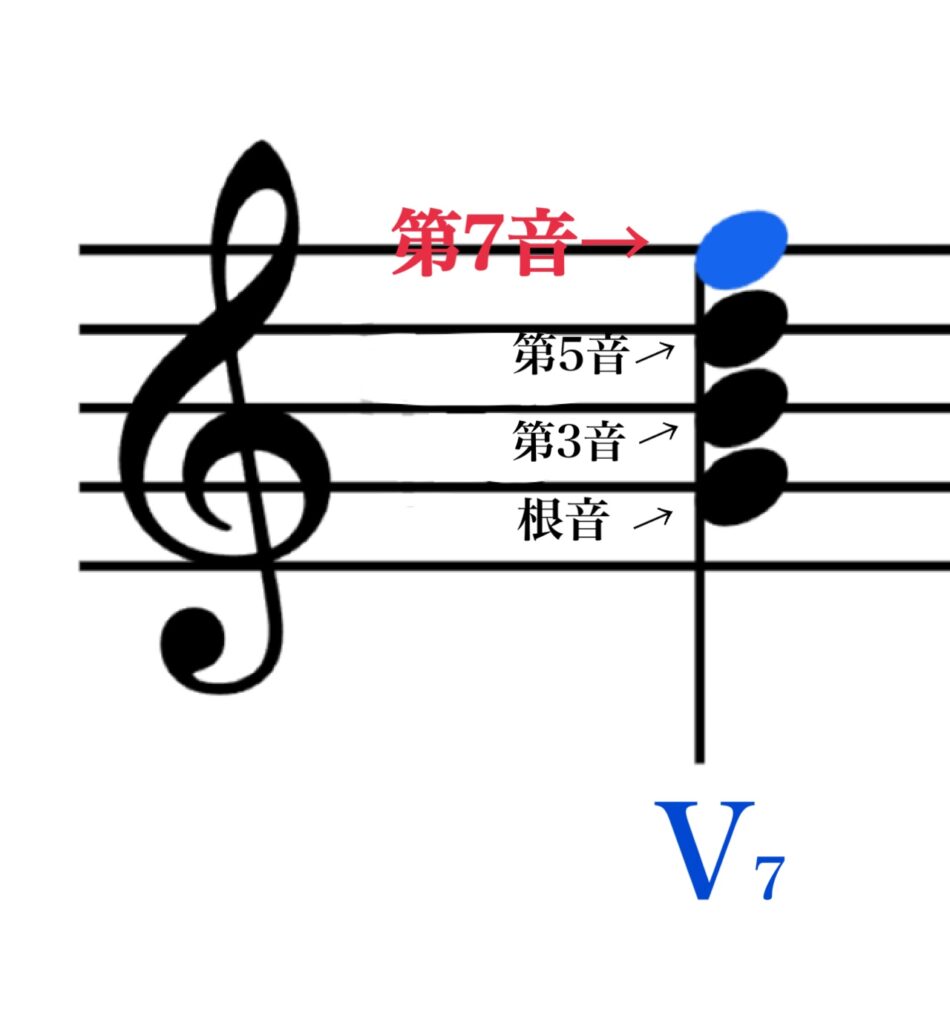
根音・・・和音の根っこの音
第3音・・・根音から3度上の音
第5音・・・根音から5度上の音
第7音・・・根音から7度上の音
ハ長調の属七の和音は上記の図の音ですが、これを和音記号で表すと、「Ⅴ」の右下に小さく第7音の「7」がつきます。
これは言うまでもなく、Ⅴ度の和音に第7音が付いていることを表しています。
ーなぜ「属七」という言葉がつくのかー
音楽用語で主音(音階の始めの音)から5度上の音(第5音)を別名【属音】と呼んでいることから由来しています。
「属音」の和音→「属和音」
属和音に第7音がついたもの→「属七の和音」
というわけです。
ドッペルドミナントを作る
属七の和音がどういうものかご理解いただけたところで、本題の「ドッペルドミナント」を実際に作って和音記号に変換したいと思います。
ここで思い出していただきたいのが、
「ドミナント」→トニックに強く向かおうとする性質をもつ。
「ドッペルドミナント」→ドミナントに強く向かいたいドミナント。
であるということ。
ドミナントはⅤ度です。(ハ長調ではソシレ)
このⅤ度の和音を主和音とする調を、ハ長調からみて「Ⅴ度調」と表します。(ハ長調のⅤ度調は「ト長調」)
「主和音」とは、音階の始めの音である主音に3度ずつ上に和音を重ねた基本の和音のこと。(ハ長調の主和音はドミソ)
そのⅤ度調(今回はト長調)に向かいたいⅤ度(第7音付き)こそ、「ドッペルドミナント」です。
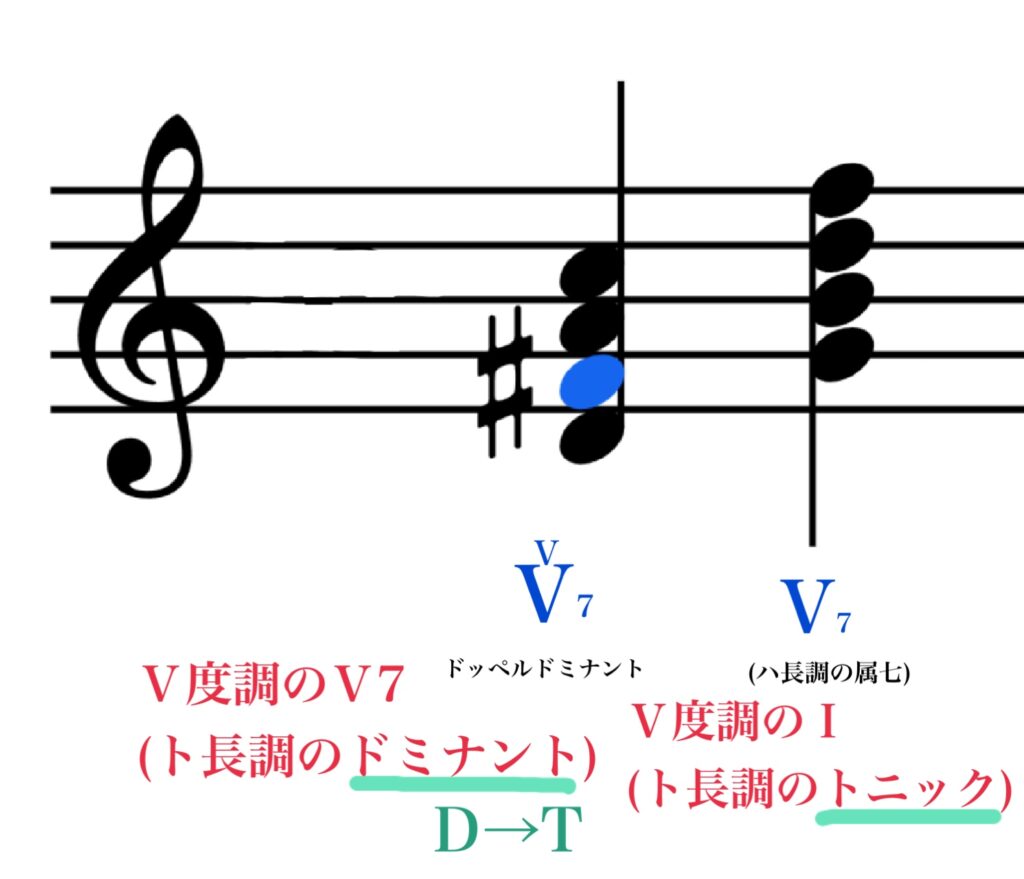
ドッペルドミナントの和音記号の書き方は、
Ⅴの和音記号の上に小さくもうひとつⅤを書き、右下に第7音を表す「7」を小さく入れれば、完成です。
まとめ
音楽のフレーズを作るのに、トニック、ドミナント、サブドミナントは必要なものですが、それだけでは変化が少なくなってしまいます。
「ドッペルドミナント」のようなドミナントに向かいたいドミナントがあることで、曲にさらなる変化をもたらします。
もう一度おさらいします。
「ドッペルドミナント」は属七の和音に属七の和音を重ねたものであり、Ⅴ度調に向かいたいⅤ度である。
和音記号は、Ⅴ7の上に小さくⅤを重ねている。
和音の種類をこれからもたくさん覚えて、より本格的に音楽を深めていきましょう。

