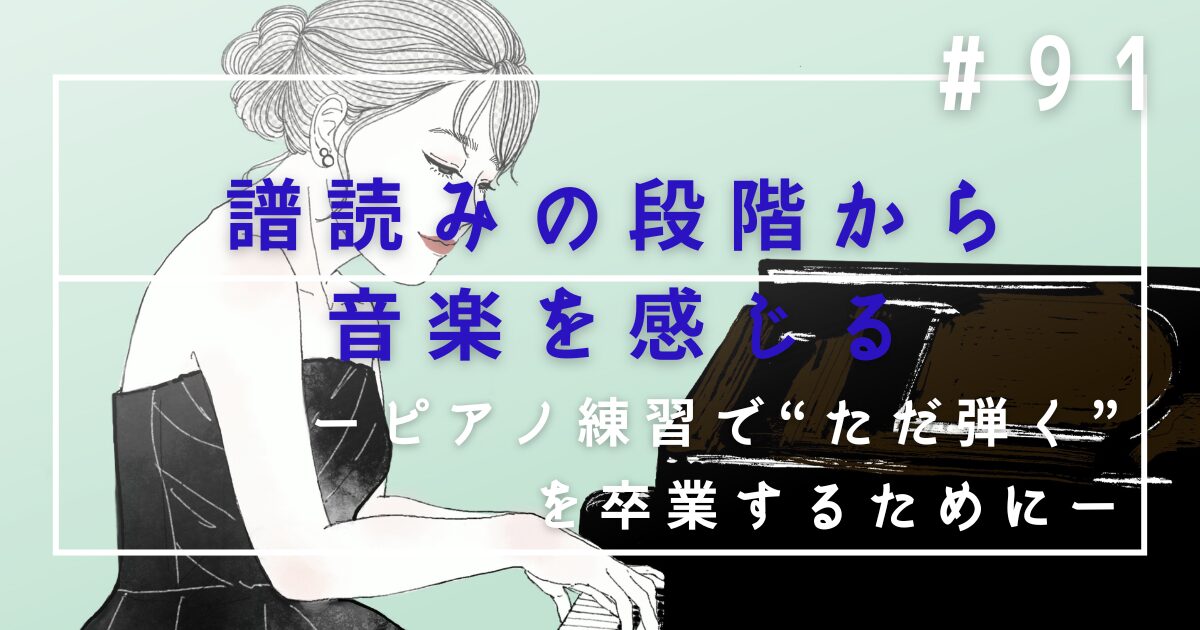ピアノを練習するとき、「譜読みの段階だからまだ音楽は後で」と思っていませんか?
ですが本当は、譜読みのときからすでに音楽は始まっています。
一音一音をただ並べるのではなく、フレーズでとらえ、響きを想像しながら弾く。
その積み重ねが、後の表現の深さをつくります。
4歳からピアノを始めて音高・音大・音大の院に進み、大人子ども含め累積約50名以上にピアノを教え、現役で演奏活動を続ける筆者が、
譜読みの段階から音楽を感じながら練習するための、私自身の意識の持ち方をお伝えします。
音源を聴いて“全体の音楽”をつかむ
私は譜読みを始める前に、まず音源を聴いて全体のイメージを持つようにしています。
どんなテンポ感や流れなのか、どんな響きが曲全体を包んでいるのかを感じておくことで、
いざ譜面を見たときにも音の方向性や色が見えやすくなります。
もちろん、誰かの演奏を真似するのではありません。
あくまで「作品の景色を感じる」ため。
音の雰囲気を身体に入れておくと、譜読みのときも“ただ読む”から“音をイメージする”という感覚に変わります。
音を“フレーズでとらえる”ことから始める
譜読みでは、私は一音ずつ読むことよりもフレーズのまとまりでとらえることを大切にしています。
どこで息を吸い、どこに流れが向かっているのか──まるで言葉を読むように。
フレーズ単位で練習すると、音単体ではなく、音の連なりとして自然な方向感が生まれます。
また、「どんな響きで弾きたいか」を想像しながら、
その響きを出すためのタッチや音量のバランスを探っていきます。
この段階ではまだ“仕上げる”必要はありません。
大切なのは、音を形ではなく流れとして感じることです。
響きを想像しながら、まとまりごとに弾く
譜読みのときは、ただ弾き進めるのではなく、
フレーズごとに止まりながら響きを確かめるようにしています。
「ここはどんな音を響かせたいか」
「どの音がフレーズを導いているか」
「和声の移り変わりはどうなっているか」
そう考えるだけで、同じ譜面でも聴こえ方が変わってきます。
譜読みを“音を探す時間”として過ごすと後からの練習も自然に深まり、スムーズに進めていけます。
音を響きで感じ取る習慣は、最初の段階から育てていきたい部分です。
譜読みから音楽を始めるという意識
譜読みを「音を頭に入れること」だと思ってしまうと、心のスイッチが入るのはずっと後になります。
ですが、最初に弾いた音からすでに音楽は始まっています。
たとえゆっくりのテンポでも、音が向かう方向や呼吸を感じながら弾くことで、音楽は自然に息づいていきます。
音をただ弾くのではなく、音で語る。
その意識を譜読みの時点から持つことが、
ピアノを“技術”ではなく“表現”として育てていく第一歩だと思います。
「イメージをもって音を読むこと」が仕上がりへの近道|筆者の経験談
私自身の感覚として、最初からどんな曲かイメージを持てていた曲は、仕上がりまで比較的にスムーズでした。
逆に、あまりイメージを持てず、ただ音を追うことから始めてしまった曲は、仕上がりまでに時間がかかったように感じます。
※私がここでいう「仕上がり」とは、「ただ音を並べて最後まで弾けること」ではなく、
「表現・音質・技術ともに練られた演奏」のことです。
別に初めから明確なイメージはなくてもいいと思いますが、大まかな方向性は初めから持っておくべきです。
行先もわからないのに、あちこち歩きまわって道に迷ってしまうのと同じです。
練習を重ねていくうちに、そのイメージをより具体化する。
その方が後からイメージを一から作るより、仕上がりまでよっぽど近道です。
今まで述べてきたことから、譜読みという作業がいかに大切なものか分かります。
「なんとなく」始めるのではなく、「イメージをもって」音を読んでいってほしいです。
まとめ
- 音源を聴いて、曲全体の雰囲気を感じておく
- 音は一音ずつではなく、フレーズでとらえる
- 響きを想像しながら、まとまりごとに弾く
- 譜読みの最初から、音楽はすでに始まっている
譜読みを“音を探す旅”として楽しむことで、
その曲はあなた自身の音で語れるものに変わっていきます。
ぜひ、譜読みの段階から音楽を作っていくことを意識して、今日から練習に取り組んでみましょう。
★お知らせ★
11月29日(土)19時~ より東京の渋谷にある「渋谷美竹サロン」にて「橋本智菜美×塩木ももこ ジョイントリサイタル」が開催されます!
大学・大学院同期の塩木さんとのコンサートは初めてです。
それぞれソロ曲も演奏しながら、連弾も弾きます。
あっという間のコンサート間違いなしです!
チケット絶賛お申込み受付中。
お申し込みの際は、chinalustig.bbb16@gmail.com、もしくはこちらのブログの問い合わせフォーム、またはコメントよりお願いいたします。