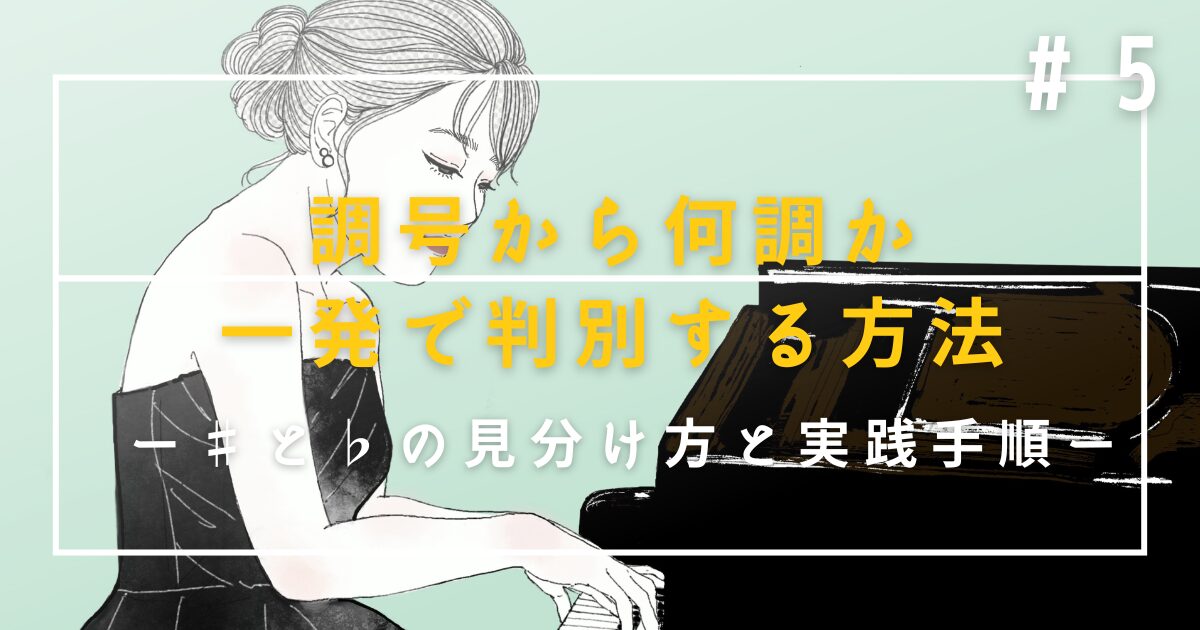楽譜を開いたとき、まず目に入る「調号」。
しかし、シャープやフラットの“数”だけを見て何となく理解したつもりになっていませんか?
実は、調号には 正しい判別手順 があり、それを知っているかどうかで
譜読みのスピードと音楽理解が大きく変わります。
4歳からピアノを始めて音高・音大・音大の院に進み、大人子ども含め累積約50名以上にピアノを教え、現役で演奏活動を続ける筆者が、
・♯と♭で異なる調判別のルール
・長調 → 短調と導く確実な方法
・絶対に引っかかりやすい落とし穴の回避ポイント
を、はじめての人でも分かるように丁寧にまとめました。
「調号から何調か一発で判断できるようになりたい」
「譜読みをもっと速くしたい」
そんな方に最適な内容になっています。
それでは早速、調号の仕組みを一緒に見ていきましょう。
はじめに(結論)
調号から「何調か」を判別するには、
まず長調を割り出し、そこから短調を逆算するのが鉄則です。
♯(シャープ)と♭(フラット)で判別方法が異なる点だけ押さえれば、
誰でも簡単に判定できます。
覚えておきたい基本(魔法の呪文)
判定をスムーズにするために、まず♯と♭の順番を覚えましょう。
- ♯の順番:ファ・ド・ソ・レ・ラ・ミ・シ
- ♭の順番:シ・ミ・ラ・レ・ソ・ド・ファ
この呪文が頭に入っていれば、実際の判別は速くなります。
♯(シャープ)の判別手順(長調→短調)
長調の判別(4手順)
- 調号の 最後の♯ を確認する。
- その音から 半音上 に上がる。
- 上がった音を 日本音名(ハニホヘトイロハ) に読み替える。
- 「◯長調」と付ければ完成。
例:♯1個(ファ♯)
最後の♯=ファ♯ → 半音上 = ソ → 日本音名「ト」 → ト長調(G dur)
例:♯3個(ファ・ド・ソ)
最後の♯=ソ♯ → 半音上 = ラ → 日本音名「イ」 → イ長調(A dur)
短調の判別(3手順)
長調が分かったら、短調は長調の主音から3度下です。
(厳密には短3度ですが、判別上は「3度下」でOK)
- 長調の主音を確認する。
- そこから 3度下 に下がる。
- 日本音名に読み替えて「◯短調」とする。
注意点(落とし穴)
3度下の音が調号で既に♯になっている場合は、「嬰(♯)」の表記になる点に注意(例:イ長調 → 嬰ヘ短調 = Fis moll)。
♭(フラット)の判別手順(長調→短調)
長調の判別(3手順)
- 調号の 最後から2番目の♭ を見る。
- その音を 日本音名 に読み替える。
- 「◯長調」と付ける。
例:♭2個(シ♭・ミ♭)
最後から2番目 = シ♭ → 日本音名「変ロ」 → 変ロ長調(B dur)
♭1個だけの特例
♭が1個だけの場合は「最後から2番目」が存在しないため、呪文の末尾をぐるっと回すイメージで ファ(F)=ヘ長調 と判定します。
短調の判別
短調は長調から 3度下げる 手順で求めます(♯と同様)。
3度下の音が調号に含まれている場合は「変(♭)」表記を付けることを忘れずに。
例:♭4個(シ♭・ミ♭・ラ♭・レ♭)
まず長調を判別。
最後から2番目 = ラ♭ → 日本音名「変イ」 → 変イ長調(As dur)
次に短調判別。
長調である「変イ長調」の主音「ラ♭ 」から3度下に下がる。(ラ→ソ→ファ)
下がった先の音を日本音名に読み替えて「◯短調」とする。
→つまり答えは「ヘ短調(f moll)」
判別が速くなる練習法(実践)
- 用意:楽譜か調号一覧を用意。
- 右手でその調の 主音(長調)を確認 → 左手で3度下を確認。
- 鍵盤で実際に その調の音階を1オクターブ弾く(長調・短調両方)。
- 例題を10個ずつやって、瞬時に答える訓練をする。
鍵盤で弾くと「響き」と「指の感触」で覚えやすくなり、譜読みが飛躍的に速くなります。
よくあるミスと対処法
- 「♯の数だけ長調を数える」などの誤解:必ず最後の♯(または♭の2番目)を探す。
- 短調判定で調号を忘れる:3度下の音が既に♯/♭かを確認すること。
- 実際に鍵盤で確かめない:必ず弾いて耳で確かめる習慣を。
感覚では覚えられなかった私が見つけた“確実な判別法”|筆者の経験談
私がここまで書いてきたような調号からの調の判別をしている人は、
他にもいらっしゃると思います。
ですが、私はこの判別方法を苦労して自分で見つけました。
私自身なんとなくではなく、理論立てないと覚えられなかったので
「どうしたら簡単に調号から調を判別できるのか」ということを必死に考えました。
その先に行きついたのが、この考え方です。
調号があっているか不安になるときは、今でも頭のなかでさっと確認します。
感覚的に覚えられる方は、本記事を飛ばしていただいて構いません。
ですが、私のようになかなか調号を覚えられないという人は、
ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。
まとめ(もう一度:手順の要点)
- まず長調を判別(♯は最後の♯→半音上、♭は最後から2番目)
- 短調は長調から3度下(調号の影響で嬰/変がつく場合あり)
- 鍵盤で弾く練習を繰り返すと定着が早い
調号の判別が身につくと、譜読みの速度と解釈力が格段に向上します。
この記事を参考に、実際にいくつかの調号で判定してみてください。
慣れれば瞬時に分かるようになります。