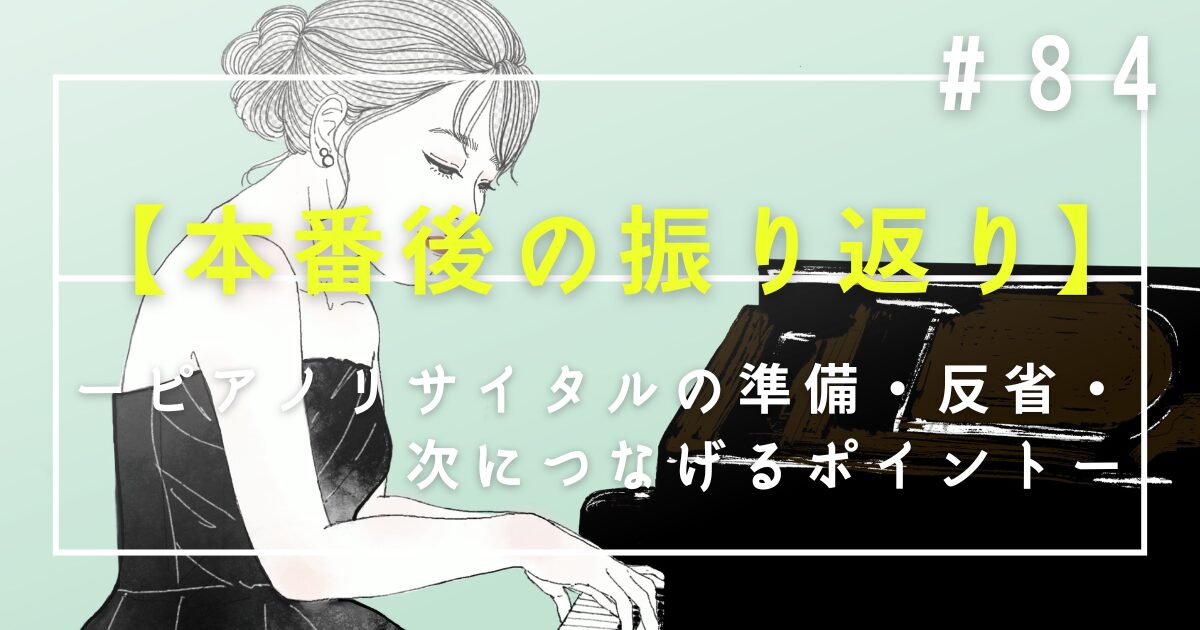2025年11月1日、与野本町にある彩の国さいたま芸術劇場・小ホールで「橋本智菜美ピアノリサイタル2025 AUTUMN 対話 ― 音楽の時空を超えて ―」を開催しました。13時開演、トークと休憩(20分)を含む90分のプログラムで、以下の曲を演奏しました。
- バッハ:平均律クラヴィーア曲集第2巻第5番 ニ長調
- ショパン:練習曲集 Op.25-10 ロ短調
- ラフマニノフ:前奏曲集 Op.23 より 第1〜4番
- ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第21番「ワルトシュタイン」ハ長調 Op.53
(アンコール:ジョン・フィールド《ノクターン第1番 変ホ長調》)
今回の記事は、この公演で得られた収穫や反省点を振り返りたいと思います。
本番の緊張と「感謝」で満たされた時間
舞台袖に立つときは、やはり緊張しました。
朝から叫びたい気持ちでいっぱいで、近所迷惑にならない程度で「あーーあーー」と言っていました。
けれど、スポットライトを浴びて舞台に出ると、会場に来てくださったお客様の姿が見えてきて──
「私はこの人たちに支えられて、ここで演奏ができるんだ。
なんて私は幸せなんだろう。」
という感謝の気持ちが自然とあふれました。
その瞬間、不思議なほど心が落ち着いたのです。
ここ数年、演奏中に緊張で足が震えることも多かったのですが、今回はそれがまったくありませんでした。
演奏に集中し、心をこめて一音一音を紡ぐことができたのは、間違いなく支えてくださった方々のおかげです。
トークを交えたステージづくり
今回は、トーク付きのリサイタルでした。
クラシックに詳しくない方にも理解して楽しんでいただけるよう、できるだけ専門的になりすぎない言葉でお話ししました。
たとえばショパンの《練習曲 Op.25-10》については、
「この曲はオクターブのエチュードと呼ばれていて、両手でずっとオクターブの動きを続けながら弾く練習曲です」
といった説明をしました。
また、曲名の最後についている「Op(オーパス)」という言葉が作品番号を意味することなども補足。
知識を共有することで、音楽がより身近に感じられる瞬間が生まれたように思います。
音楽と空間の響き
彩の国さいたま芸術劇場・小ホールは、響きが美しく、落ち着いた雰囲気のある会場です。
小・中・高・大、と学生時代コンクールで演奏した思い出のある場所でもあったので、
舞台に立ったときに胸がいっぱいになりました。
このホールでソロリサイタルが開催できたこと、そして聴いてくださる方々と音楽を通じて“対話”できたことは、何よりの幸せでした。
振り返りと今後への課題
今回の本番では、落ち着いて演奏できたという大きな収穫がありました。
以前のように緊張で体がこわばることがなく、余裕がある状態で会場に鳴る自分の音を聴けたように感じます。
一方で、客席との距離感や音のバランス、プログラム構成など、次に向けて見直したい点もあります。
特に、「お客さんをもっと呼べるようになること」が今後の目標のひとつとしてあります。
音楽を届けるということは、「聴いてくださる人がいてこそ」でもある。
あらためて、そのことを実感しました。
次のステージに向けて
日頃お世話になっているさくらMusic officeさんから「シリーズ化するのはどうか」というお話をいただいており、来年も同じ会場での公演が決まっています。
今回の経験を糧に、より深く、より自然に音楽と向き合っていきたいと思います。
来年の公演は、他楽器の人と組んでコンサートを行う予定です。ソロだけでなくアンサンブルも披露出来たらと考えています。
詳細が決まったら、こちらでお知らせします。
舞台に立つたびに感じるのは、演奏とは“自分自身との対話”であり、“聴く人との対話”でもあるということ。
これからも、その対話を大切に、音のひとつひとつに心をこめていきたいです。
まとめ|感謝と成長を胸に、次の一歩へ
リサイタルは、終わった瞬間が「次の始まり」。
本番後の振り返りは、自分を責めるためではなく、次の成長へとつなげるための大切な時間です。
たくさんの支えに感謝しながら、また新たな音の旅へ。
ピアノが与えてくれる出会いと発見を、これからも大切にしていきます。
あらためて、昨日の公演にご来場くださった皆様、素敵な機会をくださり支えてくださったさくらMusic office様、彩の国さいたま芸術劇場のスタッフの方々、お手伝いのお二人に感謝申し上げます。